
被災された方の生活を支える〈令和6年能登半島地震災害義援金〉 (日本赤十字社)にご協力お願い致します。
下の画像の右側をクリック(タップ)すると記事をご覧頂けます。

被災された方の生活を支える〈令和6年能登半島地震災害義援金〉 (日本赤十字社)にご協力お願い致します。
下の画像の右側をクリック(タップ)すると記事をご覧頂けます。
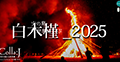


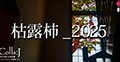


© 2023 Shiong All right reserved. 無断転載・複製を禁じます/編集・発行 編集思考室Shiong
